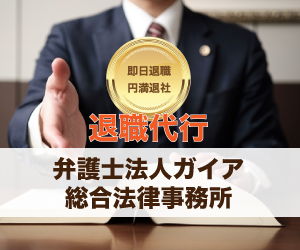退職代行サービスは、何らかの理由で自分から退職の意向を会社に伝えることが困難な場合に利用されるサービスです。
退職代行サービスを使って退職をしようと考えたとき、引継ぎの必要性について悩むでしょう。
例えば、「引継ぎをしないと迷惑がかかるが、出社したくない」と感じる方もいます。
退職代行を使えば引継ぎをせずに退職が可能なのでしょうか?
引継ぎした方が良いケース
法的には退職時の引継ぎは義務ではなく、引継ぎしないで退職することも実際には可能です。
しかし、企業にとっては引継ぎは非常に重要なことです。
次のようなケースでは、引継ぎを行うことをお勧めします。
- 就業規則で引継ぎが義務化されている場合
- 会社に大きな損失を与える可能性がある場合
就業規則で引継ぎが義務化されている場合
退職時の引継ぎが就業規則で義務付けられている場合も、引継ぎを行うことが望ましいです。
特に退職金の支給が引継ぎの完了に依存している場合もあります。
引継ぎを怠ると、退職金が減額されたり、支給されないリスクもあります。
会社に大きな損失を与える可能性がある場合
重要なプロジェクトを担当している、特定の取引先を持っているなど、引継ぎを行わないと業務に遅れが生じ、会社に大きな損失をもたらす可能性があります。
引継ぎが行われない場合、会社が取引先との信用を失い、取引が途絶えることも考えられます。
それが原因で損失が発生した場合、会社から損害賠償を求められることもあります。
引継ぎを行わないリスク
引継ぎなしで退職すると、以下のリスクが生じる可能性があります。
- 会社や顧客からの問い合わせが来る可能性
- 損害賠償請求や懲戒解雇の可能性
- 退職金が減額される可能性
これらのリスクを避けるためには、次のような事前の対策が必要です。
スムーズに退職するポイント
- 業務をできる限り完遂させる
- 基本的な引継ぎ書を準備する
- 必要であれば、退職代行サービスを通じて引継ぎなしの合意を交渉する
業務をできる限り完遂させる
業務を中途半端な状態で終えてしまうと、上司や後任者が業務の進捗状況を把握できず、効率が落ちます。退職までに業務をできるだけ完了させることで、会社側は業務の進捗を確認する手間が省け、問題も少なくなります。
引継ぎ書の作成
円満退職を目指すためには、引継ぎ書の作成が効果的です。簡易的なものでも良いので、次の人がスムーズに業務を引き継げるように、以下の情報を含めることをお勧めします。
- 関係者の氏名や連絡先
- アポイントメントの状況
- 業務のスケジュール・進捗状況
- 業務の具体的な手順
- 関連資料の保管場所
退職代行サービスの利用
どうしても引継ぎをしたくない場合は、退職代行サービスを利用して会社との交渉を行う方法もあります。引継ぎなしでの退職が合意されれば、引継ぎのために出社する必要がなくなります。ただし、この交渉を行えるのは、労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスに限られるため、利用する前には運営元をしっかり確認することが重要です。